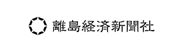
島×地方創生「一周まわって最先端」の島づくりを離島経済新聞社がレポート
vol.04
小値賀町の島々
■ ■ ■
企画書を手に、東京からやってきた男性が新たな空き家活用へ
小値賀町の新年度予算が固まりつつあった2017年1月末。東京からやってきた建設コンサルタント会社の男性が、町役場で職員に企画案をプレゼンする姿があった。
売り込んでいたのは、会社ではない。実は自分自身だった。
男性は、民間企業の社員が地方に移住し、地域の魅力向上を支援する総務省の事業「地域おこし企業人」制度を説明した上で、この制度を活用し、自分を受け入れるよう町に要望。会社で景観デザインやまちづくりに従事してきた経歴をアピールし、事業に必要な予算措置を求めた。
男性の名は、長谷川雄生。当時31歳。
「とにかく話を聞いてほしくて『押しかけた』わけですが、あとになって振り返ると、役場の担当者もよく相手をしてくれたなと……。とにかく小値賀に移住したい一心。無我夢中でした」
翌日には、予算編成の最終権限を持つ町長に直接プレゼンを行い「直談判」することに成功。
結果、熱意が伝わり、町は受け入れを決めた。
民泊先のホストファミリーと懇意になる来島者は多い
東京の会社に籍を置いたまま移住し、空き家の利活用に従事
仕事の関係で東京暮らしを続けていた雄生さんと妻の沙織さんは、2013年ごろから旅行で年1、2回は小値賀を訪れていた。
島滞在中は民泊を利用したが、「常宿」のホストファミリーをはじめ、島で頑張っている同世代などとも次第に打ち解け、顔見知りも増えていった。
ライフスタイルを変えようと地方への移住を具体的に考えるようになり、全国の「候補地」も見て回ったが、知り合いや頼れる人が多い安心感もあり、最終的に小値賀を選んだ。
移住の手がかりとして、雄生さんは役場に所属しながらまちおこし業務を手掛ける国の「地域おこし協力隊」制度の活用も模索したが、当時の勤務先の理解を得られたこともあり「企業人」制度を利用した。この制度では、会社に籍を置いたまま自治体に「派遣」される形をとる。
島での業務は、空き家の利活用が主なテーマ。各種調査やイベントの企画・運営などに携わる一方、夫婦には当初から島で宿を開くという明確な目標があり、その準備も並行して進めた。
長谷川さん夫婦が経営する民泊「暮らしを育む家・弥三」
夫婦の暮らしや日常を体験できる民泊
夫婦が経営する民泊「暮らしを育む家・弥三(やさ)」がオープンしたのは、2019年4月。起業に合わせて、雄生さんは会社も辞めた。
弥三は、築100年の古民家を改修した物件で、1日3組まで、最大収容人数8人。開業資金源は、自己資金と元会社からの出資に加え、「国境離島新法」も活用し調達した。
弥三のコンセプトは、「暮らしのおすそわけ」。自然を敬い、昔ながらの手間隙かけた暮らしを目指している夫婦の日常を体験してもらうことだ。
例えば「火のある暮らし」。電気やガスはできるだけ使わずに七輪を使ってお湯を沸かし、米を炊く。湯は、昔ながらの薪風呂。利便性とは一定の距離を置いたスタイルで、夫婦は「生きている実感がわき、自然との一体感を得られる」と魅力を語る。
雄生さんは、実は小値賀島の隣にある島の新上五島町出身で、15歳まで暮らしていた。なぜ新上五島にUターンしなかったのか、との問いに、沙織さんは「コンビニがあるんです。便利だし、つい利用したくなりますが、それでは東京にいるのと変わらないので」と話す。
民泊の舞台として古民家に着目した点について、雄生さんは「そもそも古民家は、つくりが理にかなっている」と強調する。
潮風から建物を守る板壁があり、農作業後など何かと使い勝手がいい土間もある。島の気候や風土に合致したつくり。単に昔ながらの趣を今に伝えるだけではなく、機能性も高い。
「弥三のお客様は、私たちと価値観が近い人も多い。親しくなり、一緒に旅行したり遊んだり。プライベートまで交遊関係が広がることもあって、それもまた喜びです」と沙織さん。民泊営業は、もちろん営利も目的だが、夫婦の生き方そのものでもある。
弥三では「火のある暮らし」を体験できる
安心して心から話をできる仲間
もともとコンサル会社でまちづくりなどを手掛けてきた雄生さんは、物事を企画することが得意だ。
会社員時代は、事業年度が終わってしまうと、それまでかかわっていた地域との関係も途切れてしまうため消化不良感もあった。そもそも地方への移住を考えたのも「がっつり現場に入って、思い切り仕事をしたかった」という思いが強く、小値賀という舞台で、取り組みのプラットフォームといえる仲間たちと力を合わせられることを願っている。

長谷川さん夫婦
地方では、分かりやすい移住者の「数」ばかりに目が向けられがちだが、雄生さんは「自分のやりたいことを始めたり、夢を実現させる人材がどれぐらいいるか、ということが大事では」と、人口よりは人材が重要であるとの認識。人材が育たないと、島の将来を担う後継者も育たない、と危機感を抱く。
また、UIターン者だけでなく、ずっと島で暮らしてきた人がもっと活躍できるような雰囲気も重要といい「新しいことにチャレンジしたくても、しがらみがあり一歩踏み出せない人もいるかもしれない。もしそんな障害があるのなら、一つ一つなくすことができれば」とも話す。
地方創生をめぐる議論で、必ずといっていいほど浮上する課題が「現場」における「プレイヤー」の確保。どんなに素晴らしいプランがあっても、現場で汗を流す担い手としてのプレイヤーがいなければ、絵に描いた餅になってしまう。
雄生さんが力を込める。「僕はプレイヤーの一人として民泊をはじめましたが、この経験を活かして、いろいろな人がこの島でチャレンジしやすいような環境づくりにも貢献したい」。















